本日もケンズ鉄道にご乗車いただき
ありがとうございます。
さてさて、先週の後半よりスケールトレ
インズ社GEスタンダードタービンのご予
約受付を始めさせていただきました。
「23日(日曜日)までやったね (^^ 」
今回は受付期間が10日前後と短く
て恐縮しております (^^;;
おかげさまで、すでにたくさんのご予約
を承っており御礼を申し上げます。
「そやけど、前回は”ビッグブロー”で
今回は”スタンダード”、
いったい何がちごてんの? 」
そう、スケールトレインズ社からは
GTEL 8500 ”ビッグブロー(BIG
BLOW)タービン”が2期にわたって
発売されたよね。

実は、時系列的に言うと、この”ビッグ
ブロー”はガスタービン車の第3世代と呼
ばれる1955年に登場した最終型な
んだよ。
ってことは第1世代と第2世代があった
わけだよね(^^
スケールトレインズさん、シリーズの後半
機種から製品化するなんて、まるでスタ
ーウォーズの映画化順みたいだね ・笑・
最初に言ってしまうと、今回製品化が
発表された”スタンダードタービン”は、
1952年に登場する第1世代機にな
るんだよ。
「エピソード1」みたいなもんだよね (^^
で、もっと言うとね、この第1世代の前に
航空機でタービン技術を持っていたジェ
ネラルエレクトリック社(GE)が1948年
にガスタービン車のプロトタイプともいえる
車両を作っているんだよ。
1930年代からスティームタービン車なん
かでタービン動力にすごく前向きだった
ユニオンパシフィック社がこれに興味を持っ
てGEといっしょに性能実験をするんだ。
ボディをUPイエローに塗装した4,500
馬力の車両は”UP 50”と名付けられた
そうだよ。

「この写真はHOのブラスモデル? 」
そう、BRSSTRAINS.COMさん
のご厚意でお借りしました (^_^)
このプロトタイプ「UP 50」の後に登場
する第1世代機も見てみましょう。

機番ごとに様々な改良や変更が加えられていった結果、#58と#59にも微妙な相違が複数個所にあります。
「”スタンダード”て
ゆわれてるやつやね (^^ 」
ユニオンパシフィック社は一生懸命実験
データをとったんだろうね。 機番ごとに
改良が加えられて外観が少しづつ変わ
っていくんだよ。
中でも#57は特別で、それまでの燃料
だった重油(バンカーCタイプ)から、試験
的にプロパンガス仕様に改造されたんだよ。
でも結局は、安全性の面から元の重油
仕様にもどされたようだけどね (;^_^)
今回スケールトレインズ社から発表された
テンダーなしタイプの#57は、”プロパン
タービン(Propane Turbine)”とも言わ
れる特別なプロパンガス仕様なんだ。
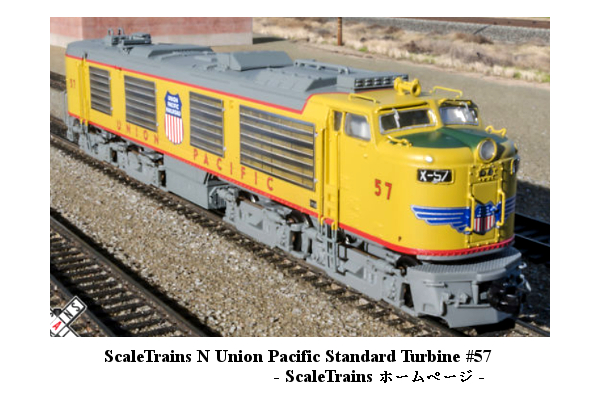
本来、#57にはプロパンタービン専用
のプロパンテンダー(タンクカー)が用意
されるべきなのですが、なぜか今回は製
品化されませんでした。
HOゲージではオーバーランドモデルズ
など、OゲージではMTHなどがシルバ
ーに輝くボディに
「UNION PACIFIC RICHFIELD」
とレタリングされたプロパンテンダーとセット
で#57を製品化しています。
「#57 propane turbine で
画像けんさくしてみてなー (^o^)/」
でも、重油仕様に戻された後を想定す
ると、通常テンダーでいいかもね (^-^)
そして、1954年に登場する第2世
代機には#61から#75が与えられ
ました。
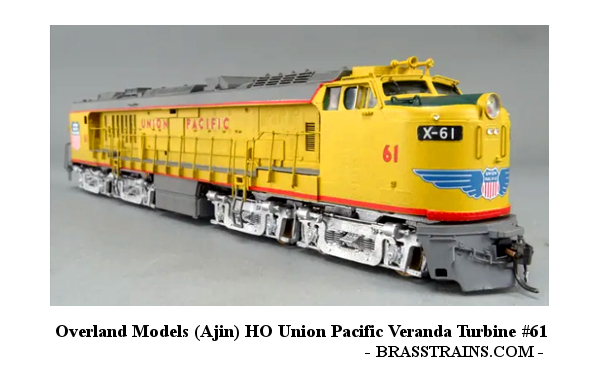
側面の通路(ウォークウェイ)が日本語に
もなっている「ベランダ(屋根下の縁側)」
に似ていることから「ヴェランダ(Veranda)」
の愛称が生まれました。
第1世代で試みられた屋上エアインテーク
が採用された結果、側面のグリルがなくな
り、特徴ある「ベランダ」の外観となります。
足回りはB+B+B+Bが踏襲されます。
「どんどん進化するガスタービン
のことがこれでようわかったわ (^-^) 」
写真をたくさん見て見るべきポイントが
いろいろわかってきたところで、今回製品
化されるNゲージの「スタンダードタービン」
を見てみよう。
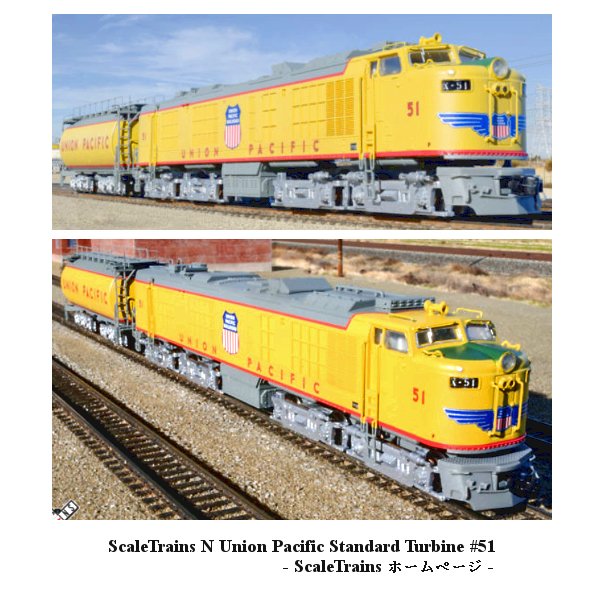
よーく作りこまれていることがよくわかる
でしょ? (^^
「前とちょっと見え方がかわったわ! (^0^) 」
来年の2月か、もしかするともうちょっと
遅れるかもしれないけれど、発売を楽し
みにしようね b(^^
タービン車の航続距離を大きく伸ばすこ
とができる22-C-GTEテンダーが別売
りで編成に増結できるのも魅力だね!
今日は、ユニオンパシフィック社のGE
ガスタービン車(GTEL)の略歴を写真
と共にご紹介いたしました。
第2世代、第3世代の礎ともなった第1
世代スタンダード(標準型)タービンは、
明後日23日(日曜日)24時まで
ご予約を受け付けておりますのでどうぞ
ご利用くださいませ。
それではみなさま、
また次回までさようなら (^0^)/
